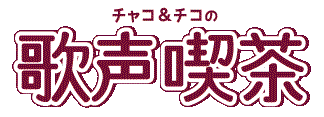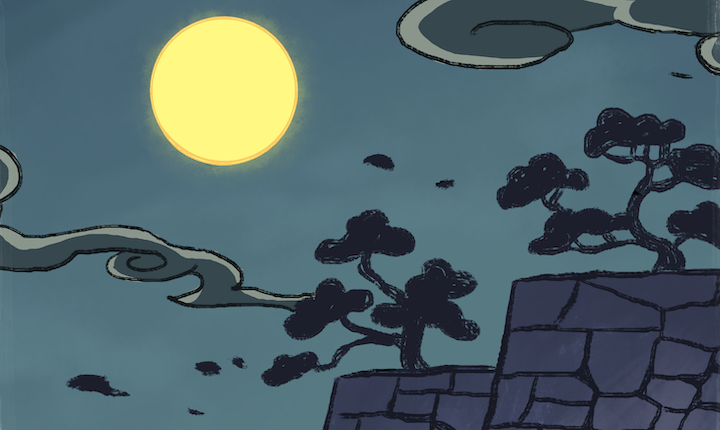明治14年『小学唱歌集』の発行により、西洋の音楽をとり入れた唱歌教育がスタートしましたが、まだまだ一般の人々が「音楽」などというものの意義について決して意識的でなかった時代、指導する教師の確保もままならず、実際には唱歌の授業が行われない学校も多くありました。
特に中学校においては教師はもちろん、題材となる歌曲も少なく、そうした状況の中で東京音楽学校の教師たちは、自らの手で音楽教育の質と芸術性を高めていくことが音楽の府としての責任であると考えます。
こうして、西洋音楽を規範としつつ現代性も備えた、若者が共感できる歌を作るべく、著名な文学者や教育者に作詞・作曲を委嘱、さらに学生たちからも作品を募集し、200曲以上を集めた中から優秀作38曲を選定した『中学唱歌』が明治34年に東京音楽学校より発行されました。
当時東京音楽学校研究科に属していた瀧廉太郎が応募用に作った三曲「豊太閤(ほうたいこう)」「箱根八里」「荒城の月」はすべて採用され、ここに収められました。
【参考文献】
堀内敬三・井上武士 『日本唱歌集』 (岩波書店)
宮瀬睦夫 『滝廉太郎伝』 (関書院) ※
※:国立国会図書館デジタルコレクション