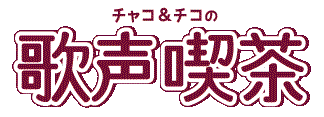うつくしくも憂いのあるメロディーとゆったりとしたスウィングのリズムでつづられるロマンティック・ブルース歌謡。戦後まもないこの時期に、歌に描かれる「別れ」とは、単なる恋愛沙汰でない理不尽な喪失を語っているのかもしれません。作詞作曲家・東辰三氏はそれをあくまでも一編のロマンスとして描ききり、聴くものが身を委ねられるモダンなスローブルースにのせました。
昭和21年、戦災によりレコード製造が不可能な状況にあった日本ビクター社は、復活を目指し全国から歌手を募集、約3000人の中から7人の新人歌手を採用します。そのうちの一人が平野愛子さんでした。
東辰三氏は彼女のために柔らかなブルース調の新曲を作り、ビクターのレコード制作部の上山敬三氏との話し合いの末、桜をモチーフにゆく春を惜しむ歌詞をのせることになりました。出来上がった歌は社内で評判がよく、ベテラン歌手からも歌わせてほしいという申し出があったそうですが、“新しい時代に新しい歌手の歌声を”という上山氏の強い意向があり、新人歌手・平野愛子さんによる歌唱を譲らなかったといいます。
平野愛子さんの物憂げな歌声は人々の疲れた心にやさしく溶け込み「港が見える丘」は大ヒット。デビュー曲で一気に人気歌手へとかけ上がりました。
詞・曲をてがけた東辰三氏(あずま・たつみ 本名:山上松蔵 1900〜1950)は東京・深川出身。江戸っ子で辰巳の生まれ、という洒落がペンネームの由来です。戦前の日本に和製ポップスの礎を築いた歌手・作曲家の中野忠晴氏のスカウトにより、昭和10年にジャズ・コーラス・グループの「コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ」に参加。
その後、作詞作曲の能力をみこまれてビクターに入社します。当時としてはめずらしく、作詞と作曲の両方をおこなうスタイルで、持ち前の洒落心とセンスを活かした広告音楽作家としての夢を抱きつつ、戦時体制下の音楽家として軍国歌謡「荒鷲の歌」で頭角を現します。
戦後はラジオ歌謡「風はそよ風」、平野愛子さん歌唱の「港が見える丘」「君待てども」「白い船のゐる港」のようなモダンな和製ポップス、竹山逸郎さんの「泪の乾杯」など戦前流行歌風の味わい深い作品もヒットしました。
昭和25年に51歳という若さで亡くなったことが惜しまれます。もしながく生きていれば、昭和20〜30年代の歌謡界をさらにおおくの名曲でいろどったことでしょう。
ところで「港が見える丘」の各コーラスの以下の部分、
一番:船の汽笛むせび泣けば チラリホラリと花びら
二番:船の汽笛消えてゆけば チラリチラリと花びら
三番:船の汽笛遠く聞いて ウツラトロリと見る夢
聴くものの聴覚と視覚をスローモーションの世界へといざなう、この歌のなかでも特徴的な一行です。現在発売されているCDなどの歌詞カードやインターネット上の歌詞情報では、上記のように表記されていることがほとんどだと思うのですが、平野愛子さんの歌唱音源をあらためてじっくりときいてみると、どうもつぎのようにうたっていることに気づきました。
一番:船の汽笛むせび泣けば チラリホロリと花びら
二番:船の汽笛消えてゆけば キラリチラリと花びら
また後日、昭和22年発売のSP盤に付属している歌詞カードを写真で見ることができました。そこにはまちがいなく「チラリホロリ」「キラリチラリ」と書かれていたのです。
なるほどこのカタカナ部分は単に花びらを形容しているだけでなく、「私」の心のありようを花びらにかさねて言いあらわしている、まさしくこの歌の“肝”となるフレーズだったようです。一番では心がゆれうごく“ホロリ”、二番では涙の“キラリ”。これが花びらの“チラリ”とオーバーラップするしかけです。
コーラスグループで喉を鳴らし、流行歌作家としては作曲家よりも先に作詞家としてデビューした東辰三氏の作品は、こうした細やかな歌心・詩心がベースにあるのだということがあらためて感じられます。
そしてその詩心は昭和40〜50年代の歌謡史に名を刻んだ大作詞家・山上路夫氏(東辰三氏の息子)にたしかに引き継がれたのだと思います。
【参考文献】
『日本の流行歌〜歌でつづる大正・昭和』上山敬三・著(早川書房)※1
『音・その歩み・その夢:ビクター音の開発史』(ダイヤモンド社)※2
『中野忠晴の功績とその評価 ─主に戦前期から─』近藤博之・著
『レコード音楽技芸家銘鑑 昭和15年版』(レコード世界社)※3
『歌暦五十年』丘灯至夫・著(全音楽譜出版社)※4
『アサヒグラフに見る昭和の世相7 昭和23-24年』(朝日新聞社)※5
◎この曲のチコ編曲によるギター独奏用楽譜は以下の店舗またはオンライン楽譜販売サイトで購入できます。